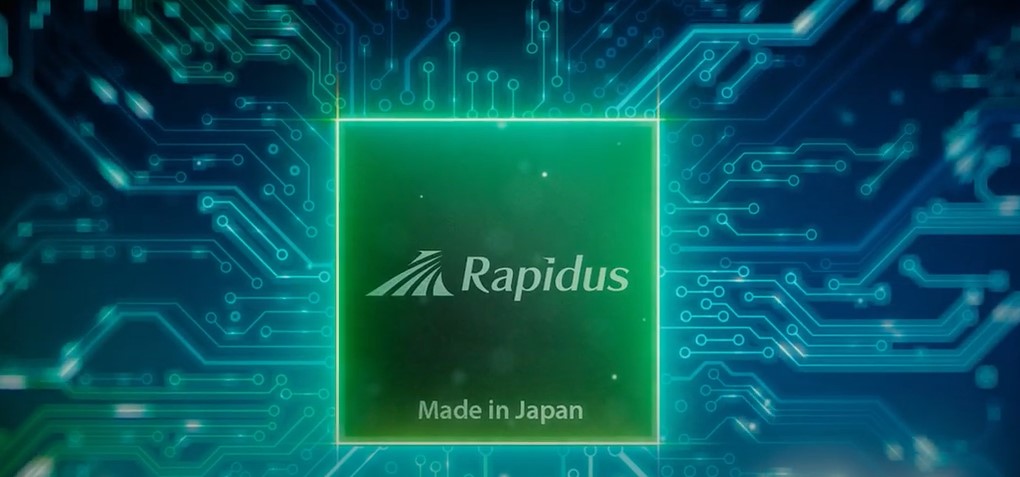
日本のラピダスは、TSMC、インテル、サムスンといったファウンドリ大手が独占しているとされる2nmチップの開発を進めており、注目を集めている。
日経新聞によると、同社は4月に試作を計画しており、6月までに2nmのサンプルを提供することを目指している。
ラピダスの可能性を十分に理解し、不確定要素を明確にするため、TechNewsコラムニストの林良陽氏(国立高雄師範大学准教授)は、同社が2nm量産に向けて克服しなければならない3つの重要な課題について論じている。
初期の難題: プロトタイプから製品への転換
eeNews Europeの過去のレポートによると、ベルギーの経済使節団が来日し、2022年後半に協力覚書を交わした後、ラピダスは2023年にimecのコアパートナープログラムに参加した。新ファウンドリーは、IBMの半導体専門知識と2nmプロセスを利用する計画も発表した。
しかし、ラピダスは、林氏のコラムで強調されたように、研究所の結果の限界に留意すべきである。
IBMのトーマス・J・ワトソン・リサーチ・センターは有名な機関ではあるが、現在は研究に重点を置いており、最新の「ゲート・オール・アラウンド」(GAA)プロセスはまだラボ段階である。
同様にimecも、半導体に長けているとはいえ、量産経験が乏しい研究機関である。
林は、彼らの技術が商業化できるかどうかが、ラピダス社の大きな課題になると指摘する。
2nm量産への挑戦は弱まる?
今のところ、FinFET(Fin Field-Effect Transistor)が主流であり、TSMC、サムスン、インテル、UMC、GlobalFoundries、SMICなどの大手企業が豊富な経験を有している。
では、なぜラピダスはGAAに賭けるのか?
林の見解では、ラピダスはGAAを、特にAIやHPC向けに、より優れたパフォーマンスとエネルギー効率を提供する次世代技術だと見ている。
加えて、TSMCの日本工場が22/28nmと16nmを採用する予定であることから、GAAに投資することで、ラピダスが政府補助金を獲得できる可能性が高まるかもしれない。
しかし、日本の半導体技術は現在40nmと遅れているため、設立からわずか2年半のラピダスが2nmプロセスへストレートに飛躍できるかどうかは重要な課題である。
特に、新しいGAAプロセスはFinFETアーキテクチャーよりも複雑で、林氏の記事で強調されているように、精度管理、材料欠陥、放熱、リーク電流、材料界面の問題などの課題に直面している。
独自の生産モデル: 治療薬か毒か?
ラピダス・デザイン・ソリューションのアンリ・リチャード初代社長によると、同社は当初、AIチップの新興企業を主な市場としており、TSMCと直接競合しなくても成功できると考えていた。
林氏の記事では、EUV装置と規模に限りがあるため、ラピダスのいわゆる大量生産は主流とは異なり、ニッチ市場向けの多角的な小規模生産に注力し、他の大手企業とは一線を画していると指摘している。
米半導体大手のブロードコムがラピダスの2nmチップの顧客になるかもしれないという噂は、有望なスタートを意味する。
実際、ラピダスの成功は、Rapidus-IBM-imecの協業が高品質で高性能なチップを確実に提供するためのリーダーシップにかかっている。
その小規模で多角的な生産モデルが鍵になる可能性があり、それがうまくいけば、林氏の記事にあるように奇跡が起こるかもしれない。
ソース:TrendForce - [Insights] Exploring Rapidus’ Path to 2nm Mass Production: 3 Key Challenges Ahead
解説:
トレンドフォースにラピダスの現状に関する記事が出ていましたので取り扱ってみます。
ラピダスは4月に2nmの試作、6月にサンプルの出荷を予定しているとのこと。
しかし、量産に至るにはまだ厳しい道のりが待っているようです。
対するTSMCは今年から量産可能にはなっているものの、高コストに音を上げてAppleですから採用を見送ったほどです。
おそらく来年にはアップルが採用することになると思われますが、ラピダスの量産開始予定は2027年ですから、本来2年の遅れがあったところが1年になったということになります。
半導体製造のコストはどんどん上がっており、最新プロセスが量産可能になってもアップルですら二の足を踏むようなコスト高になっています。
もう一般向けの機器には最新プロセスが使えなくなるかもしれませんね。
ラピダスの戦略はAI向けの新興チップをターゲットにしているということで、非常に素晴らしい戦略なのではないかと思います。
需要も見込めますし、新興企業とは言ってもブロードコムといえば通信チップ企業の大手ですから、AIの分野が新興というだけで、別にまったくの新規参入というわけでもありません。
一時期Intelで生産するというようなニュースがありましたが、ラピダスでの生産も視野に入れているようですね。
秒進分歩の半導体業界において、地歩を固められるかどうかは遅れなく量産にこぎつけられるのかどうかにかかっていると思います。
電子立国とまで言われた日本の半導体業界が日米半導体協定で敢無く潰えてしまった経緯を見てきたわたくしにとっては2nmという最先端プロセスで不死鳥のごとく復活する姿をぜひとも見てみたいと思いますし、そう願ってやみません。